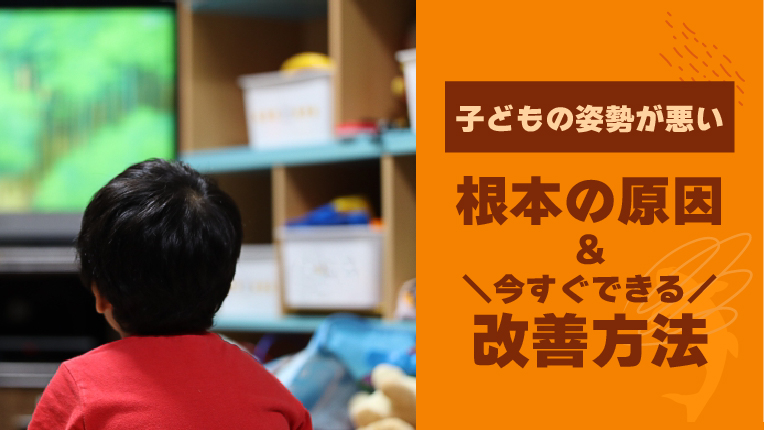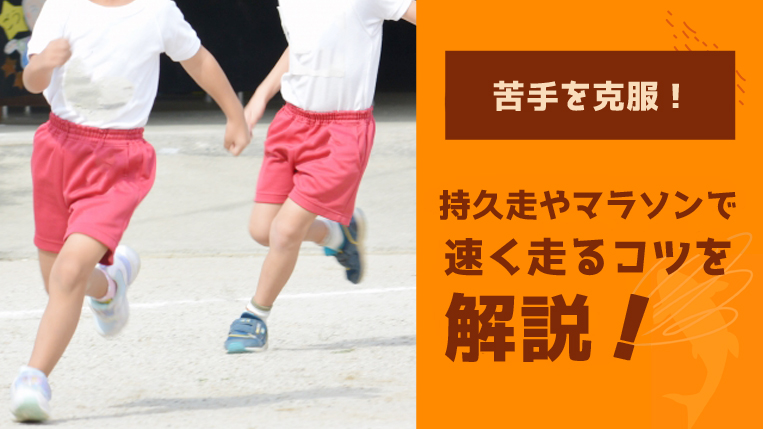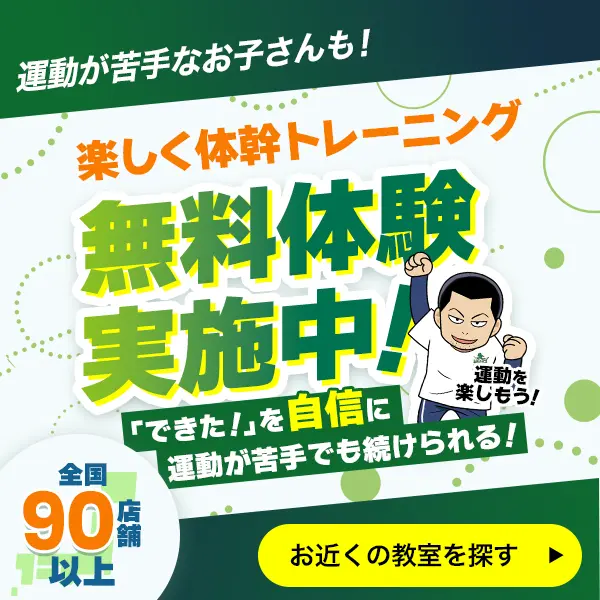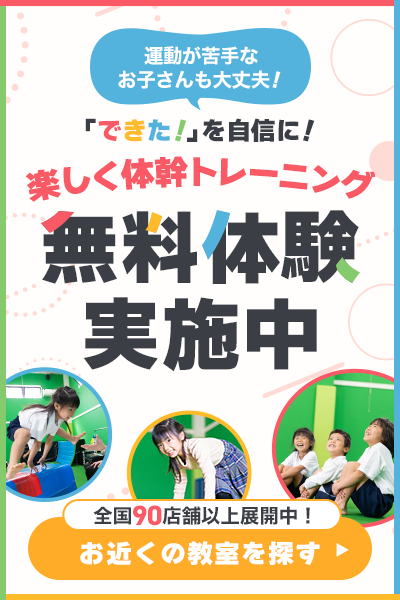「自分で考えて行動できるようになってほしい」「失敗から学んで次に生かす力を身につけてほしい」子どもを見守る中で、そう感じることはありませんか。
自分の考えや行動を客観的にとらえ、改善につなげる力を育てるために、今注目を集めているのが「メタ認知」です。
メタ認知を意識したトレーニングを取り入れると、学習やスポーツ、人間関係など、さまざまな場面で力を発揮できるようになります。
本記事では、メタ認知とは何かを解説し、子どもにとっての重要性や、家庭で実践できる効果的なトレーニング方法を紹介します。親子で楽しみながら取り組み、考える力を着実に育てていきましょう。
目次
メタ認知とは?

「メタ認知」とは、自分の考えや行動を一歩引いた視点から客観的に見つめ、コントロールする力です。
例えば「今のやり方で合っているかな?」「もっと良い方法はないかな?」と考えることも、メタ認知の一種であり、十分な力が備わっていると、状況に応じて自分を調整し、より良い行動を選択できるようになります。
メタ認知を意識して育てることで、学習やスポーツの場面で自分の弱点を把握し、改善に向けて行動を変えられるようになります。
さらに、失敗を恐れず次の行動につなげる力も養われ、挑戦する意欲が自然と高まっていくでしょう。
子どもにとってメタ認知が重要な理由

メタ認知は、成長期の子どもにとって特に大切な力です。
客観的な視点を持つことで、失敗を恐れず挑戦できるようになり、自己管理能力も高まります。ここでは3つの観点から、メタ認知の重要性を解説します。
自分の行動を客観視できるようになる
メタ認知力が育つと、子どもは自分の行動を冷静に振り返り、「次はこうしよう」と改善点を見つけられるようになります。
例えば、テストで間違えた問題を分析して「ここは時間配分を工夫すれば解けた」と気づけば、次のテストでは時間を考え、計画的に取り組めます。
一方で、メタ認知力が弱いと、テストで同じミスを繰り返したり、失敗を人のせいにして改善が進まなかったりするでしょう。
客観視できる力があるかどうかで、学習だけでなく友達関係やスポーツでの成長スピードも大きく変わってきます。
失敗から学び、挑戦を続ける力が育つ
失敗を「終わり」とせず、「学びのチャンス」と捉えられるのもメタ認知の力です。
例えば試合に負けたときも、原因を分析して「次は何を変えるべきか」と考えられれば、次の挑戦につなげられます。
反対にメタ認知力が育っていないと、「どうせ無理」と諦めて挑戦そのものを避けてしまいがちです。
挑戦と改善を繰り返す経験は成功体験を積み重ね、自己肯定感をしっかりと育てます。
社会人になってからも困難を乗り越える場面は多く、冷静に状況を分析し行動を修正できる力は大きな支えとなります。
現代社会を生き抜く「折れない心」を育むためにも、メタ認知は欠かせない力といえるでしょう。
将来の自己管理・問題解決能力につながる
メタ認知は、成長するにつれて学習・スポーツ・人間関係など、さまざまな場面で力を発揮します。
メタ認知が高い子どもは自分の行動を客観的に修正できるため、学校生活では学習の進め方を工夫し、効率よく成果を上げられるようになります。
スポーツでは試合の流れを冷静に判断し、状況に応じて戦術を変えられる柔軟さも身につきます。
さらに人間関係では、相手の立場を考えて行動できるため、トラブルを未然に防ぎ、より良い関係を築けるはずです。
反対にメタ認知が弱い場合は、トラブルが起きても感情的に対応して問題を悪化させたりする可能性があります。
幼少期からメタ認知を鍛えておくことで、社会に出てからも冷静に状況を分析し、柔軟に課題を乗り越えられるようになります。
家庭でできる!メタ認知を育てるトレーニング法5選

メタ認知は、特別な教材や時間を用意しなくても、日常の中で楽しく育てられます。
ここでは、家庭で簡単に取り入れられる5つのトレーニング方法を紹介します。
「振り返りタイム」を取り入れる
1日の終わりやスポーツ・学習の後に「今日うまくいったことは?」「次の目標は?」など、話し合う時間を設けましょう。
成功も失敗も言語化することで、自分の行動を客観的に振り返る習慣がつきます。
また、どんな小さな気づきでも共有することで、子どもは自分の成長を実感しやすくなるでしょう。
例えば「今日は声を出して練習したら上手にできた」といった発見を積み重ねると、次の行動につなげる意欲も高まります。
親子で前向きな振り返りを続け、トレーニングを積み重ねていくことで、自然とメタ認知力が育っていきます。
役割を変えて考える「逆質問タイム」
宿題の解き方やルールの説明など、身近なテーマを取り上げて「もし友だちにこの問題を教えるなら、どう説明する?」と問いかけてみましょう。
説明する立場に立つことで、自分がどこまで理解できているかに気づきやすくなります。
さらに「どうすれば分かりやすく伝えられるか」を考える過程で、情報を整理しながら話す力も養われます。
質問を「まず何から説明する?」「次はどう伝える?」と段階的に進めていくと、子どもも考えやすく、自然とメタ認知力が高まりますよ。
会話の中で自然と始めやすく、効果的なトレーニングなので、ぜひ気軽に取り入れてみましょう。
目標と振り返りをつなぐ「ステップアップシート」
紙に「今日の目標」と「やってみて気づいたこと」を書き出すだけで、行動と振り返りが自然に結びつきます。
例えば「縄跳び30回連続成功」を目標に掲げ、挑戦後に「リズムを意識すると跳びやすかった」と記録すると、自分の成長が可視化され、次の行動につなげやすくなります。
また、記録を続けることで、達成感が積み重なり、自己肯定感も育まれるのが嬉しいポイントです。
学習ではテスト勉強、スポーツでは練習内容など、さまざまな場面で活用できるトレーニング方法なので、ぜひ幅広く取り入れてみてくださいね。
複数の解決策を考える「もしもゲーム」
「もし宿題を忘れたらどうする?」「雨でイベントが中止になったら?」など、身近な状況を想定し、子ども自身に解決策を考えてもらうトレーニングです。
1つの答えにとどまらず複数の方法を出すことで、柔軟な発想と冷静な判断力が養われます。
さらに、それぞれの解決策に対して「どんな結果になるか」も一緒に考えると、先を見通す力も身につきます。いざというときにも落ち着いて対応できる自信にもつながりますよ。
気づきを引き出す「問いかけコミュニケーション」
子どもが何かに悩んでいるときは「どうしたらいいと思う?」と問いかけ、自分で考える時間を与えましょう。親がすぐに答えを示すのではなく、考えるヒントを少しずつ出すことで、子どもの思考力がぐんと伸びます。
ゆっくりじっくり、子どもの考えを引き出すトレーニングを重ねることで、親子の絆も深まり、自分で解決策を導き出す力が育っていきます。
子どもの「考える力」を伸ばす!メタ認知トレーニングの効果と家庭でできる方法|まとめ
メタ認知は、子どもが自分を客観的に見つめ、成長につなげるために欠かせない力です。
トレーニングを通じて鍛えることで、学習やスポーツの成果が上がるだけでなく、将来の自己管理力や問題解決力といった社会で役立つ力も身につきます。
家庭での簡単なトレーニングを取り入れ、親子で一緒に考える習慣を重ねていくことが、子どもの自信と行動力を育てる第一歩です。日々の生活の中で無理なく続け、未来につながるメタ認知能力をしっかり育んでいきましょう。
JPCスポーツ教室 お近くの教室を探すあわせて読みたい関連記事
- 体幹とは?よくある誤解と正しい知識を徹底解説!
- スキー上達につながる体幹トレーニングと実戦で役立つ呼吸法を解説
- マラソンが速くなるトレーニングとは?小学生でも挑戦できる練習法を解説!
- 背が伸びるスポーツはある?身長が伸びる関係性とおすすめの運動を紹介
- 体幹トレーニングで子どもの身長が止まる?身長が伸びる仕組みを解説
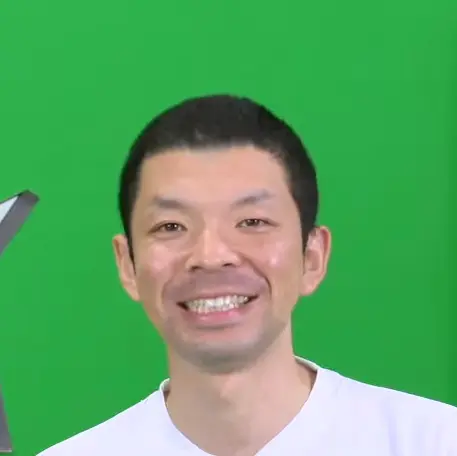
羽島本店
経歴
岐阜県内の幼稚園、保育園で体操指導員として2010年より10年間指導にあたり、現在JPCスポーツ教室羽島本店の指導員として在籍中。
SV(スーパーバイザー)として主に愛知エリア・九州エリアの店舗管理を行う。
資格
KOBA式体幹トレーニング Sライセンス
NESTA キッズコーディネーション トレーナー
子ども身体運動発達指導士