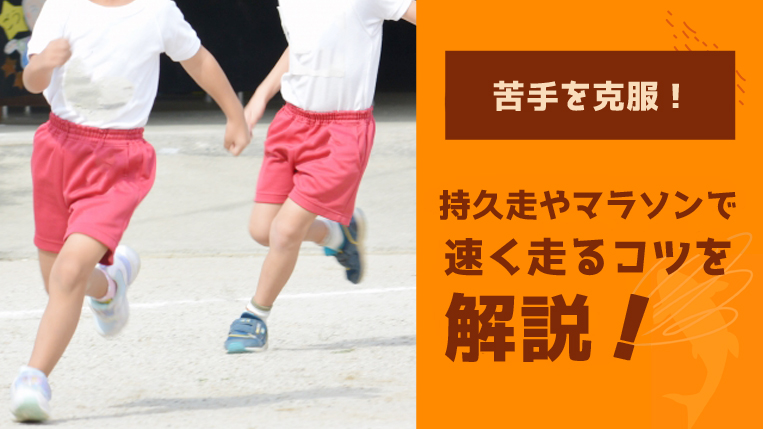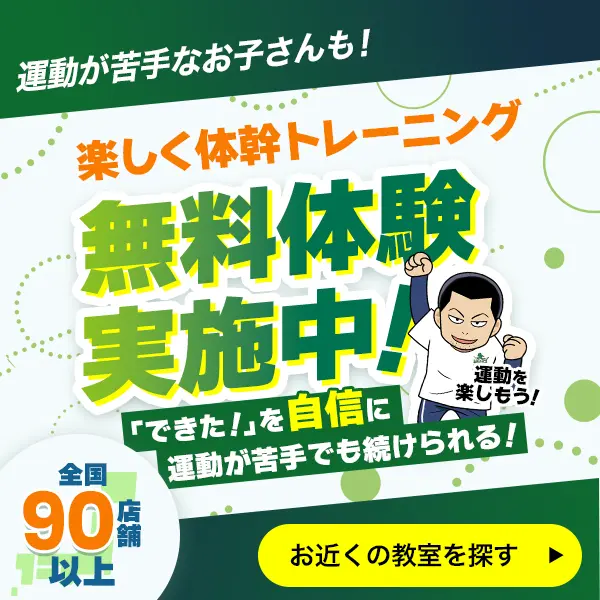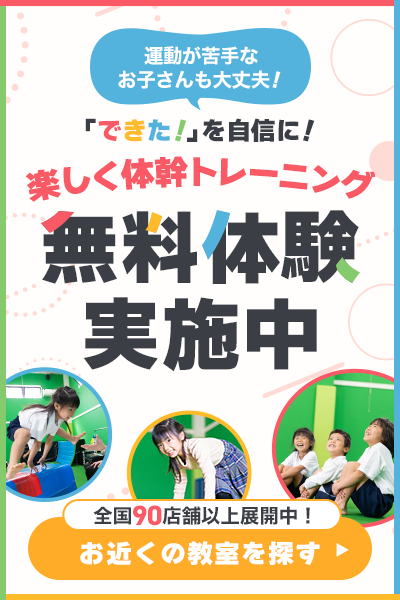けん玉と聞くと、昔ながらの遊びを思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし実は、けん玉には「体幹」「集中力」「バランス感覚」など、子どもの成長に欠かせない力を楽しく育てられる要素が詰まっています。
本記事では、初心者でも楽しめるけん玉の基本の技や「かっこいい」「すごい」と注目されるような大技、練習のポイントなどを紹介します。
子どもとのおうち時間をもっと有意義にしたいとお考えの方や、遊びを通して集中力やチャレンジする力を育てていきたいと感じている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
けん玉はただの遊びじゃない!トレーニングにも役立つ理由

けん玉は、動く玉を目で追い、タイミングを合わせて技を成功させる必要があるため、視覚と動作の連動を鍛えるビジョントレーニングに最適です。
さらに、姿勢を保ちながら全身を使うことで、体幹トレーニングやバランス感覚を養う効果も期待できます。
ここでは、けん玉がどのように視覚力と体幹を育てるのか、特徴と魅力を紹介します。
動く玉を目で追う!動体視力を鍛えるビジョントレーニング
けん玉では、常に動く玉を目で正確に追い、キャッチのタイミングを瞬時に判断します。「見る→判断→動く」という一連の流れこそがビジョントレーニングであり、繰り返し練習することで動体視力が鍛えられるのです。
さらに、目で捉えた情報を素早く処理して体を動かす力が伸び、玉のスピードや軌道が毎回変化することで反応速度や空間認識力も自然と磨かれていきます。結果として、スポーツや日常生活でも、物を素早く捉え、的確に行動できるようになるでしょう。
遊びながらバランス感覚と集中力が身につく
けん玉は、「玉を皿に乗せる」「けんに刺す」といった一見シンプルな動作に見えて、実は高度なバランス感覚と集中力が求められる遊びです。わずかな手の角度や力加減で成功が左右されるため、子どもたちは自然と慎重に体を動かすようになっていきます。
また、成功するたびに達成感を得られるだけでなく、集中して繰り返し取り組む姿勢も身についていきます。習慣化することで、勉強やスポーツにも通じる大切な力となり、継続力の土台づくりにもつながるでしょう。
けん玉は全身を使った運動!姿勢や体幹も自然に整う
けん玉は、技を成功させるために、足をしっかり踏ん張り、ひざを柔らかく使い、背筋を伸ばして構える必要があります。自然と「正しい姿勢」と「体幹を意識した動き」が求められるため、知らず知らずのうちに全身が鍛えられていきます。
また、動きにメリハリをつけることも重要になるため、力のコントロールやリズム感を養うのにも効果的です。遊びの延長でここまで多くの力が鍛えられるのは、けん玉ならではの魅力です。
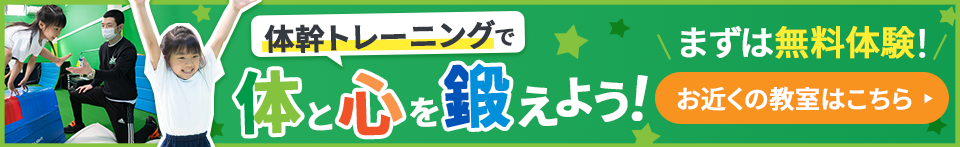
初心者におすすめ!基本のけん玉技3選

けん玉には数百種類もの技があるといわれていますが、最初の一歩は「基本技」から始めるのがおすすめです。基本技をしっかりマスターすることで、自然と体の動かし方やけん玉の扱い方が身につき、より難しい技にもスムーズに挑戦できるようになります。
ここでは、けん玉初心者でも楽しみながら取り組める、3つの基本技を紹介します。
まずはここから!「大皿・小皿・中皿」
けん玉の基本中の基本といえるのが、「皿に玉を乗せる」技です。けん玉には大きさの異なる3つの皿(大皿・小皿・中皿)があり、それぞれに玉を乗せるだけでもバランス感覚が求められます。
- 大皿:けんの一番大きな面。初心者でも乗せやすく、最初に挑戦したい技。
- 小皿:けんの反対側にある小さな皿。玉が落ちやすく、コントロール力が必要。
- 中皿:けんの持ち手の中央にある皿。手元に近く、姿勢の安定がカギ。
玉の動きをよく見て、ひじから下をうまく使うことがコツです。
まずは、大皿から挑戦してみましょう。玉をまっすぐ下に引いて、軽く膝を使いながら玉をふわっと持ち上げ、落ちてくるタイミングで皿を玉の下にすべらせるように動かすと、成功しやすくなります。
慣れてきたら、小皿や中皿にも挑戦して、バランスの感覚を養っていきましょう。
シンプルだけど奥が深い「とめけん」にステップアップ
「とめけん」は、皿ではなく、玉をけん先のとがった部分に刺す技です。見た目はシンプルでも、成功させるには集中力とタイミングが必要です。
まずは、けんをまっすぐ上に構え、膝を使ってふわっとやさしく玉を引き上げます。焦らず、玉が落ちてくるタイミングを見極めて、けんの先端をそっと差し込むようなイメージで練習してみましょう。
はじめはうまくいかなくても、繰り返すうちに力加減や玉の動きが自然とつかめるようになります。挑戦の先に、「できた」という達成感が待っていますよ。
リズム感が鍛えられる「もしかめ」に挑戦!
「もしかめ」は、「大皿」と「中皿」に交互に玉を乗せ続ける連続技です。「もしもしかめよ」のリズムに合わせて行うことから、名前が付けられました。
技のポイントは、テンポよく、同じ動きを繰り返すこと。ひざを軽く使って、リズミカルに体を上下させることで、自然とリズム感や持久力が身についていきます。
親子で一緒にやってみると、遊びながらのコミュニケーションにもなって一石二鳥です。成功回数を競い合ったり、曲を流しながら取り組んだりするのもおすすめです。
できたらすごい!かっこいいけん玉技2選

基本技に慣れてきたら、次は「かっこいい」「すごい」と注目される少し難易度の高い技に挑戦してみましょう。大技にチャレンジすることで、モチベーションがグッと高まります。
ここでは、体幹や集中力を存分に活かせる2つの人気技を紹介します。どちらも練習が必要ですが、できるようになると達成感もひとしおです。
灯台|体幹と集中力を極めるバランス技
「灯台(とうだい)」は、玉の上にけんを立てるというバランス技です。けんをまっすぐ静かに立てて静止させる必要があるため、繊細なコントロールが求められます。
まずは、玉を軽く引き上げてけんをふわっと浮かせ、皿部分をそっと玉の上にかぶせるように合わせましょう。けんの軸がブレていないかを意識することが成功のカギです。
難易度が高い技ですが、練習を重ねて灯台ができるようになると、周囲から「すごい」「かっこいい」と注目されること間違いなしの実力派の技ですよ。
飛行機|スピード感と回転のあるクールな技
「飛行機」は、玉を持ってけんを振り上げ、回転させたけん先を、空中で玉の穴にスッと差し込む上級技です。けんが飛行機のように着陸するイメージからこの名が付きました。
まずは、玉を持って構え、膝を使ってけんを振り上げます。けんが回転するタイミングを見ながら、けん先を静かに穴に差し込みましょう。技を成功させるには、玉の動き、けんの角度、回転タイミングを正確にコントロールする必要があります。
体幹や手首の安定がとても重要で、回転とスピードを合わせて決まると「すごい」「かっこいい」と歓声が上がる、派手で高難度な技です。
けん玉が上達するコツと練習法

けん玉は、ポイントを押さえて、効率よく練習することで、驚くほど早く技を習得できるようになります。ここでは、けん玉がどんどん上達するためのコツと、日々の練習法を紹介します。
正しい姿勢が上達への近道
けん玉の基本は、正しい姿勢から始まります。足を肩幅に開き、ひざを軽く曲げて、背すじをまっすぐに保つことで、体全体のバランスが取りやすくなります。姿勢が崩れていると、玉の動きも不安定になり、思うように技が決まりません。
また、けん玉を持つ手だけでなく、ひじや肩の位置も意識しましょう。肩に力が入っていると動きがぎこちなくなるため、できるだけリラックスして構えるのがコツです。
毎日5分でもOK!親子で続けることが大切
けん玉は、短時間でも毎日コツコツ続けることが大切です。たとえ5分でも、毎日続けることで体や動きの感覚がつかめるようになり、上達スピードが格段にアップします。
特におすすめなのは、親子で一緒に練習することです。競争したり、技を見せ合ったりすることで、楽しみながら継続できるうえ、親子のコミュニケーションにもなります。
「今日は何回成功できたかな?」「上手になってすごいね」と、声かけをするだけでも、モチベーションの維持に大きな効果がありますよ。
けん玉の技に挑戦しよう!できたらすごい&かっこいい技を紹介|まとめ
けん玉は、子どもたちの体幹や集中力、バランス感覚を楽しみながら育てられる、まさに「遊びとトレーニング」が融合した道具です。大皿・とめけん・もしかめなどの基本技から始めて、灯台や飛行機といったかっこいい技に挑戦することで、達成感や自信も自然と育まれます。
JPCスポーツ教室では、この「見る力」と「動く力」を組み合わせたけん玉を使ったビジョントレーニングがスタートしました。
けん玉で養った集中力やバランス感覚をスポーツ全般に活かすことができます。遊びながら脳と体を一緒に育てる環境として、ぜひチェックしてみてください!
JPCスポーツ教室 お近くの教室を探すあわせて読みたい関連記事
- ビジョントレーニングとは?子どもの集中力や運動能力を高める方法
- ドッジボールが運動神経の育成に役立つ理由!その他に鍛えられる能力も解説
- 鬼ごっこトレーニングが体幹・持久力強化につながる理由と練習法を解説!
- 海外にも運動会はあるの?日本の運動会との違いや珍しい競技を徹底解説!
- 【子どもの姿勢が悪い】姿勢が悪くなる原因と今すぐできる改善方法!
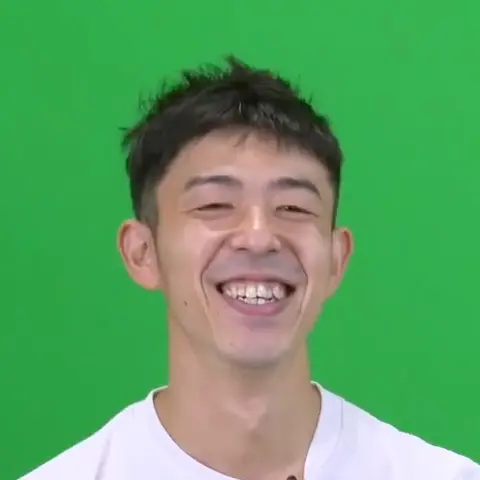
羽島本店
経歴
岐阜県立岐阜城北高校卒業後、中学硬式野球クラブチームの監督を2年間務める。(全国大会ベスト4)
現在JPCスポーツ教室の本部統括を務め、羽島本店の指導員として在籍中。
SV(スーパーバイザー)として主に関東エリアの店舗管理を行う。
資格
KOBA式体幹トレーニング Bライセンス
KOBA式体幹トレーニング Aライセンス
KOBA式体幹トレーニング Sライセンス